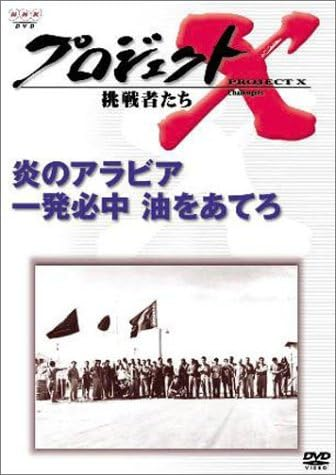いい加減だった就活
今から30年以上も前の私の就活は人には言えないくらいにいい加減だった。
時はバブル全盛期。大学としては名の通っている早稲田大学の理工学部卒業が見込まれていたため、わがままを言わなければ一流企業と言われている会社のどこかには楽に入れる状況だった。しかし、学科が資源工学科で専攻が探査工学という少し変わった勉強をしていたことや、将来への展望も特に無いくせに変なこだわりがあったため、就活は困難を極めた。
親戚を頼って入ろうとしたシンクタンクは4大卒では難しかったようで諦めた。同期の多くが検討していた国産電機メーカーは肌に合いそうになかった。あるとき友人と府中にある電機メーカーの工場を訪問したら、同窓の先輩社員が歓待してくれたが、お昼休みのチャイムとともに、社員の方々が社食に走り込むのを見て、この会社では働けないと思った。ソニーには憧れたが、電気専攻でなかったため、入社試験の情報を得ようとした電話で門前払いを食った。
なんとなく雰囲気で外資系コンピューターメーカーが良いのではないかと思い、当時は横河電機の資本がまだ入っていたHP(当時の社名は横河ヒューレットパッカード、通称YHP)を訪問した。コンピューターだけよりも計測機器があった方が経営が安定してそうに思えたのと、自分もどちらかというと計測の方があっているのではないかと思ったからだ。
会社訪問後、そろそろYHPをちゃんと受けるかなぁと考えていたら、同じ研究室の2個上の大学院の先輩が先にYHPを受けてしまった。その年、その研究室からは私とその先輩しか就職は予定しておらず、先輩は私が先にYHPにあたりを付けていたにも関わらず、「及川くん、同じ研究室から2人も同じ会社は良くないよ。及川くんはDECが良いんじゃない?」と自分が落とされたばかりのDECを勧めてきた。YHPにさほど強い思い入れがあったわけでもない私はDECに書類を送った。
当時の記憶が曖昧なのだが、DECに書類を送るのが遅かったのか、選考プロセスに時間がかかったのかわからないが、夏近くになっても、まだ最終面接にもたどり着いていなかった。さすがに、焦った私は他に興味の持てそうな会社ということで、TBSとアラビア石油にも応募した。TBSは友人が受けるというから一緒に受けただけなのだが、技術職枠。TBS社内の見学ができて楽しかった。こちらはほとんど選考が進まないうちに他の2社が決まったので辞退したはずだ。
最後まで選考が進んだのが、DECとアラビア石油。DECから内定が出た翌日にアラビア石油から役員最終面接があるので来てくれという電話がかかってきた。形式的なものと言っていたので実質的な内定通知だった。すでにDECに決まっていたので、辞退したが、DECからの内定通知が1日~2日ずれていたら、私はアラビア石油に就職していたことだろう。
その頃のことはデベロッパーのキャリアと働き方を語ろう vol.2の中のインタビューで語っている(今見たら、Kindle Unlimitedだと無料で読めるようなので、是非読んで下さい)。
アラビア石油という会社
このアラビア石油という会社、今の方はあまり知らないだろう。今でもまだある会社だが、私が就活していた頃とはまったく違う会社になっている。
話は私が生まれる前の昭和30年代に遡る。戦後からの復興を果たし始めた日本であるが、経済成長のためのエネルギー供給については欧米の石油メジャーに完全に依存していた。これを脱するには、日本が自ら中東に鉱区を持たなければならないとの信念のもとに、サウジアラビアとクウェート両国との交渉の末に採掘権を獲得し、石油の開発をスタートさせたのが、アラビア石油だ。一時は法人所得ランキングでトップになったこともある。
自分が就職していたかもしれない会社ということや大学の同期が石油関係や資源探査関係の会社で働いていたこともあって、常にアラビア石油のことはどこかで意識していた。就活時に、アラビア石油に入社することになったらサウジアラビア勤務になるとも聞かされていたので、中東の情勢にも他人よりは関心が深かったと思う。社会人になってしばらくたって起きた湾岸戦争もテレビニュースを食い入るように見ていた。
21世紀を迎えようとするころ、この会社は大きな危機を迎えた。アラビア石油がサウジアラビアとクエートで採掘を行っていた鉱区の利権の更新が行えなかったのだ。サウジアラビアは多額の費用が必要とされる鉱山鉄道の開発と運用を要求してきた。この会社の成り立ちからしてそうなのだが、もはや一企業の判断ではなかった。実質的な国家間の交渉の中、アラビア石油と日本は利権の延長を諦める。そして、数年後にはクエートとの交渉にも失敗した。
鉱区を失ったアラビア石油は経営合理化を進める。当時330人いた社員は180人とほぼ半減にすることになった。それに伴い、希望退職者が募られた。希望退職者には割増退職金が支払われるが、残留希望したとしてもそれが叶うか、また叶ったとしてもいつまで会社が存続するか不明だったこともあり、2週間の募集期間のうちに全社員が応募したようだ。一方で、当面のオペレーション継続のために一定数の社員は確保しなければならないという事情もあり、再雇用希望者も募った。
当時、そこまでの内情は知らなかったのだが、鉱区延長に失敗した結果、全社員が1年ごとの契約社員となったというように理解していた。ちょうど石油公団が不良債権問題により廃止されたのも同じころだった。アラビア石油にも石油公団にも、大学の先輩や後輩がいたこともあり、自分ごとのようにこれらのニュースを見ていたことを思い出す。
その後、アラビア石油は精製部門の子会社だった富士石油とともに統廃合を繰り返すなどして今に至る。正直、今がどうなっているか良くわからない。
アラビア太郎
歴史となってしまったアラビア石油だが、なんで急にこの話を思い出したかというと、去年ダイヤモンドで次のような記事があったからだ。
- 消えた超高収益企業・アラビア石油、「日の丸油田」を掘り当てた山下太郎の生涯(上) | The Legend Interview不朽 | ダイヤモンド・オンライン
- 消えた超高収益企業・アラビア石油、「日の丸油田」を掘り当てた山下太郎の生涯(下) | The Legend Interview不朽 | ダイヤモンド・オンライン
アラビア石油の創業者の「アラビア太郎」こと山下太郎氏のことは名前は知っていた。しかし、その生涯についてはぼんやりとしか知っていなかった。このダイヤモンドの過去の経営者インタビューを再掲した記事で、初めてアラビア石油創業者山下太郎氏の肉声を目にする機会を得た。(脱線するが、週刊ダイヤモンドは大正2年創刊という歴史を持つ。知らなかったので、かなり驚いた)
私が学生時代に勉強していた資源探査というのはその性格上、山師的な人が多くいる。
山師とは何か。
職業として鉱脈を見つけ出す専門職のことをもともとは意味していたと思うが、鉱脈を見つけることのように可能性が低くても、当たれば大きいものを狙うことから、大博打を打つことを好む人を指すようになった。
山下太郎氏はまさに最後は資源探査という本来の山師であったが、それに至るまでに行った事業でも、博打という意味での山師であったようだ。どんなことをした人かというと…
クラーク博士で有名な札幌農学校(現 北海道大学)何かでかいことをしたいと思っていた彼は、オブラートの工業化を行う。そしてそれを成功させた後、事業を売却し、次に行った雑穀やブリキの取引で一財産を築く。好景気にも支えられ、鉄材や肥料など手を出すものすべてがうまくいった。ロシアからの鮭缶の輸入では革命後のどさくさで約束を不履行にされそうになるも、人脈を辿り当時外務省の秘書官だった松岡洋右氏経由で国を動かし、解決する。その後も硫化アンモニウムや米の取引を行う。米は当時米不足に悩んでいた日本のために、輸出が禁じられていた中国から輸入を試みた。国家を巻き込んだ密輸入なのだが、最後の最後にそれは失敗する。しかし、内地での使用に流用することで決着をみた。第二次世界大戦中は満州で満州鉄道の住宅建設などを請負い、大儲けをする。この頃は満州太郎と呼ばれていたようだ。しかし、戦後、財産はすべて没収される。数行で書いたが、この1つ1つがそれだけで自伝として本にできそうなほどにドラマがある。どれもとてつもなくスケールがでかい。
ダイヤモンドの記事の中でも山下氏は次のように言う。
私は山師、大いに結構と言う。
いま、それどころか、この世に一番大事なものは山師の根性ではあるまいか。山師の根性なくして、なんの事業ぞや、と言いたい。
山師の定義を投機とするならば、儲け主義に見え、軽蔑の対象とさえなろう。しかし、山下氏の言う山師にはそこに大義がある。彼が師と仰ぐ松本烝治氏(幣原内閣での憲法改正担当国務大臣を務めた商法学者)からは「山下こそは信義の人である。士魂を持った事業家である」と言われたという。
この山下氏が大義を持って人生最後に取り組んだのが、先に紹介したサウジアラビアとクエートからの鉱区獲得だった。この事業に取り組み始めたのが69歳のときだったというのに驚かされる。人生80年時代、いや100年時代と言われる今とは違い、55歳で定年を迎え、60歳では隠居生活に入って頃の話だ。そのバイタリティと知的・肉体的な体力は称賛に値する。
ダイヤモンドの記事(有料)でも彼の半生や人物像はわかる。しかし、さらに知りたくなった私は次の書籍をさらに読んでみた。
この小説仕立てで書かれた書籍から知る彼の人生は、まさに波乱万丈。大正から戦後までの時代とともに駆け抜けた彼の人生哲学と行動原理がわかる。今の時代にはそぐわない部分は多くあれど、今の日本に欠けているものも多く見つけられるだろう。
事業や経営には、浪漫と算盤が必要と言われるが、彼の成功の裏には常に浪漫がある。「でかいこと」の定義には大義がある。それにさらに彼ならではの人脈づくりと投資手法が加わり、アラビア石油という歴史的偉業へと繋がったのではないか。
浪漫とは、新しいものを見つけたいという気持ちだろう。早世した私の出身研究室の教授も探査の研究を続ける理由は浪漫だと言っていた。私が研究室に配属になってしばらくして海外留学に旅立ってしまった先生とはあまり直接お話する機会が無かったのだが、ある時の飲み会で生意気にも「探査って地下構造を知ること、すなわち人間の未知の世界を知ることの1つだと思うんですよね。浪漫ありますよね」とか話しかけたら、ぼそっと「浪漫しか無いよ」と先生も言っていたのを思い出す。ここじゃないどこかに行きたいという気持ちが浪漫だ。(ちなみに、高校時代は文学部史学科を志していたこともあった。早稲田大学の吉村作治先生のエジプト調査隊に憧れたからだ)
この本、昭和臭が強いので好き嫌いが分かれると思うが、元気を貰いたい人、今の閉塞感漂う状況を打破したいと思う人は是非とも読んでみて欲しい。
日本の科学技術への理解
社会がパンデミックの驚異にさらされて早くも1年以上が過ぎようとしている。この中で、我々日本人が知ることになったのは、科学技術立国であるはずの日本の現状だ。もちろん、まだまだ日本が先端である分野も多い。しかし、検査体制の拡充やワクチン開発やワクチン接種の遅れ、様々なデータの不備、IT活用の未熟さなど、目を覆いたくなるような現実を見せつけられた。このような状況はバブル崩壊後に特に顕著になったと思っていたが、実はそうでも無いのかもしれない。
書籍「アラビア太郎」の中にもあるエピソードが語られる。敗戦が濃厚になる中、山下氏が気のおけない仲間と交わした米国の兵器の優秀さをきっかけとした会話だ。曰く「日本の飛行機は目的地に着く前に電波探知機で捉えられ撃ち落とされてしまう」「B29は中が気密になっていて、1万メートル上空でも地上と同じように呼吸ができるが、日本の戦闘機は風防ガラス1枚でおおわれているだけなので呼吸困難になり気絶してしまう」。
これに対して、科学技術の問題かという知人に対し、別の知人が「経済力の問題だ」と答える。
「それはね、こういうことなのだ。日本の科学は、理論面では相当の水準に達している。アメリカやイギリスにくらべて、そんなに見劣りしないところまでいっているのだ。ただ、それを技術面に生かすことができない。技術の開発には、設備だとか人手が必要だが、それには膨大な金がいるからね。大学や研究所で、いくら金がいるといっても、政府はなかなか出そうとしないのだ」
「それはそうだ。さっきのB29のはなしだが、飛行機の内部を気密にするくらい、理論的には簡単なことなのだ。理論といえないくらいのものだ。ただ、それをやるには、金がいる。逆にいえば、金さえあれば、われわれにだってB29くらいの飛行機が作れないことはないということになる。しかし、役人たちにいわせれば、気密なんて贅沢だという。金持ちの息子の遊覧飛行じゃあるまいし、住み心地のいい部屋の中でチューインガムを噛んだり、口笛を吹いたりしながら、戦争ができるものかというのだ。結果はどうかといえば、チューインガムを噛んだり、口笛を吹いたりしている連中に、撃ち落とされるということになる」
「こんなことも聞いたよ。墜落したB29の残骸を調べてみたら、電波探知機のアンテナに”ヤギ”というマークが入っていたそうだ。つまり、日本の八木博士が発明したアンテナだね。八木博士がこのアンテナを完成したとき、政府へ採用を申し入れたが、陸軍も海軍も、見向きもしない。結局、アメリカから高い特許料で買いに来たので、売ってしまったのだそうだが、そのむくいを、今われわれは空襲という形で受けているわけだ」
この会話をどこかデジャヴュに感じてしまうのは私だけだろうか。
参考情報
このブログ記事を書くにあたって、記憶が曖昧だった、2000年当時のアラビア石油の情報を探していて、次の資料にたどり着いた。
まず、アラビア石油社員でいらっしゃった前田高行氏の「挽歌・アラビア石油 (私の追想録)」。ご自身のブログで連載されていたものが一括してPDFで読めるようになっている。これは力作である。中途で入社されたアラビア石油の1976年~2000年までのことを中の人の言葉で書かれている。アラビア石油の最後だけでなく、湾岸戦争のときの様子などが書かれている。不勉強にして存じ上げなかったが、著者の前田高行氏は中東研究者として著名な方のようだ。中東関係の書籍もいくつか出されている。
もう1つ参考にしたのが、こちらのサイトだ。
Yellow Hiro's TOPIC#2-14b アラビア石油
こちらは鉱区の利権延長交渉のニュース記事をクリップしたものだが、当時の緊迫感が伝わってくる。